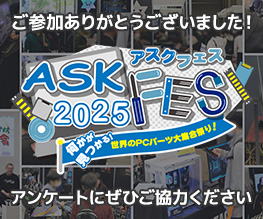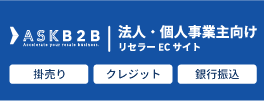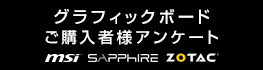マザーボードは各パーツを取り付ける、自作PCで必須のパーツだ。しかし、細かな仕様については案外知らないもの。購入した後に思っていた仕様と違う、機能が使えない等のトラブルが起こることは度々ある。そうした誤解を避けられるよう、今回はマザーボードの選び方をスペックの読み方を確認しながら紹介しよう。自作PC用のマザーボードは基本的に海外製なので、スペック表の表記が英語の場合も多い。できるだけそちらもフォローしていく。
目次
対応CPUの確認
対応TDPにも注意
CPUの対応は、大きくIntel製とAMD製に分けられる。CPUソケットの形状が異なるため、間違うことはあまりないだろう。対応CPUの項目にはいずれかのCPUシリーズが記載されているため、使用するCPUに合わせて選べばよい。
MSIの「PRO Z690-A」の例。「12th Gen Intel Core」とあるように、Intelの第12世代のCoreシリーズと、その同世代のPentium Goldシリーズ、Celeronシリーズに対応している。
注意点としては、そのマザーボードより後に発売したCPUには正式に対応していないため、BIOS(UEFI)のアップデートが必要な場合がある。特にAMDプラットフォームは1つのCPUソケットを何世代にも渡って使い続けることが多く、CPUの取り付けはできるものの動作しないという事態が起こりやすい。メーカーによって異なるが、基本的に対応するBIOSのバージョンは対応CPU一覧から確認できる(MSIの場合は対応するバージョンのBIOSをダウンロードできる)。
Mini-ITXなど小型のマザーボードを中心に、プラットフォームとしては対応しているものの、個別のマザーボードがTDPの高いCPUに対応していないというケースもある。TDPが100Wを超えるCPUを使う場合は、念のため確認しておくとよい。
対応CPUはおおむねチップセットで決まるため、チップセットとCPUソケット、CPUの対応関係を覚えておくと製品選びがしやすくなる。
チップセットで製品の位置付けを確認
マザーボードのおおまかな仕様が分かる
チップセットはマザーボードの機能をまとめる役割を担っており、ここからおおまかな仕様が分かる。ただし、マザーボードのスペック表ではチップセットの型番以上の情報は掲載していないことがほとんどだ。
チップセットは最上位モデルが最も多機能で、下位モデルになるほど機能が減っていく。モデル間の差となるのはCPUやメモリーのオーバークロック対応、PCI Expressの総レーン数、USB端子の数など。各チップセットの特性を覚えておくと製品選びに役立つが、特定のマザーボードの仕様を調べる上ではそれほど重要ではない。チップセットの仕様は複雑な上、マザーボードはチップセットの備える機能を全て搭載しているわけではないためだ。
Intel Z690を例に、USBの仕様を見てみる。USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)を最大4個、3.2 Gen 2x1(10Gbps)を最大10個、3.2 Gen 1x1(5Gbps)を最大10個、USB 2.0を14個利用できるという仕様だが、全てを利用できるわけではない。
Intelのチップセットは「Flexible High Speed I/O」という機能を備えており、一定の範囲で高速なデータバスの役割を変更できる。USB 3.xに割り当てられたデータバスは10本で、5Gbpsと10Gbpsは1本、20Gbpsの端子は2本利用する。そのため配分によってはUSB 3.x端子は最大6個というケースもあり得る。画像はIntel Z690のデータシートからの引用。
基板のサイズ(フォームファクター)
規格はあるものの、実際のサイズはまちまち
基板サイズは規格で決まっているが、必ずしも守られているわけではない。サイズ感の確認というよりも、PCケースと合わせる際の参考にするとよいだろう。
| 規格の名称 | 標準サイズ |
|---|---|
| Mini-ITX | 約170×170mm |
| microATX | 約244×244mm |
| ATX | 約305×244mm |
| Extended ATX | 約305×330mm |
| SSI-CEB | 約305×266mm |
標準サイズから外れる場合は、基本的に小さくなる。大きくなるとPCケースに収まらないが、小さい分には問題ないためだ。例えば270×200mmのようにATXより大幅に小さいマザーボードでも、長辺がmicroATXよりも大きいため、これはATXとして扱われる。
通常のタワーケースを使用するのであればあまり影響はないが、小型のPCケースでは内部スペースに少し余裕が生まれるため、組み立てがしやすくなる場合もある。
メモリーの仕様
CPUによって制約がある場合も
対応するメモリーの仕様は少し複雑だ。順番に見ていこう。
まずメモリースロットの本数。これによって最大容量も決まる。2022年8月現在、コンシューマー向けDDR4/DDR5メモリーの1枚あたりの最大容量は32GBなので、スロットが2本なら最大64GB、4本なら128GBとなる。大容量が欲しい場合はメモリースロットが4本のマザーボードを選ぶと良い。
動作クロック
次に動作クロックを確認しよう。スペック表では、非オーバークロック状態での対応クロックと、オーバークロック時の最大値が記載されている。オーバークロックしない場合は対応している中で最も高い動作クロックのメモリーを選べば問題ない。ただし、CPUによって対応するメモリーの動作クロックが異なる場合もある。併せて確認しておこう。
複雑になるのがメモリーの種類による制約だ。オーバークロック時の最大値は、使用するメモリーモジュールの種類や構成によって変化する。
メモリーのランク
メモリーモジュールがメモリーチップを管理するまとまりを「ランク」と呼ぶ。CPUのコア数に似た考え方で、2ランクのメモリーモジュールは1枚で内部的に2枚相当として扱われる。ほとんどのメモリーモジュールが1ランクまたは2ランクだ。ランクの数が増えると管理の手間も増えるため、構成によって最大クロックが変わる場合もある。上図のスペック表で「1R」や「2R」とあるものがそれだ。
「DPC(DIMM Per Channel)」はチャンネルあたり何枚のメモリーモジュールを取り付けるかを表す。例えば「1DPC 1R Max speed up to 5100MHz」とある場合、1ランクのメモリーモジュールを1チャンネルあたり1枚(デュアルチャンネルの場合は最大2枚)使用した場合は5100MHzに対応するという意味。メモリーモジュールが2ランクになると4000MHzになる。内容を以下の表にまとめた。ランク数の合計値が大きくなると最大速度は下がるのが基本だ。
| スペックの表記 | 内容 | スロット1-3、2-4の組み合わせでデュアルチャンネルになる場合の搭載例 |
|---|---|---|
| 1DPC 1R Max speed up to 5100 MHz | 1チャンネルあたり1ランクのモジュールが1枚の場合、最大5100MHz | 1R/-/-/-、1R/-/1R/- |
| 1DPC 2R Max speed up to 4000 MHz | 1チャンネルあたり2ランクのモジュールが1枚の場合、最大4000MHz | 2R/-/-/-、2R/-/2R/- |
| 2DPC 1R Max speed up to 4266 MHz | 1チャンネルあたり1ランクのモジュールが2枚の場合、最大4266MHz | 1R/1R/-/-、1R/1R/1R/1R |
| 2DPC 2R Max speed up to 3600 MHz | 1チャンネルあたり2ランクのモジュールが2枚の場合、最大3600MHz | 2R/2R/-/-、2R/2R/2R/2R |
オーバークロック用プロファイル
「XMP」や「A-XMP」はメモリーモジュールに搭載されたオーバークロック用情報(プロファイル)のことだ。オーバークロックメモリーは非オーバークロック状態の動作情報も備えており、初回起動時はそちらの設定で動作する。BIOSでXMPを有効にすることで製品のスペックにあるオーバークロック設定を利用できる。
デュアルチャンネル
「Dual Channel(デュアルチャンネル)」はメモリーの高速化機能だ。メモリーへのアクセス経路(チャンネル)を2本用意し、並列にアクセスすることで高速化する。2本あるチャンネルにそれぞれメモリーを追加すると有効になる。優先して利用するメモリースロットが指定されているのはこの機能のためだ。
ECC
「non-ECC, un-buffered memory」はECC非搭載、アンバッファードタイプのメモリーに対応するという意味。ECCとバッファードは共に業務向けシステムで利用する機能なので、コンシューマー向けのPCでは通常利用しない。反対に、ECC搭載やバッファードに対応したメモリーは通常コンシューマー向けマザーボードでは動作しないため、間違って購入してしまわないよう注意しよう。
拡張スロットとM.2スロット
対応規格や排他仕様に注意
拡張スロットの仕様は少し複雑だ。現行プラットフォームでは、Intel系、AMD系ともにCPUとチップセット双方にPCI Expressコントローラーを備えている。あるスロットはPCI Express 4.0、別のスロットは3.0という風に対応が分かれるため、どのスロットがCPUとチップセットのどちらに接続しているかが記載されている。CPUに接続しているスロットは、使用するCPUによってPCI Expressのバージョンが変わることもある。
拡張スロットとストレージの項目。こちらも画像はMSIのMAG X570S TOMAHAWK MAX WIFIのものだ。「PCI_E1」や「M2_1」の表記は、各スロットの番号。マザーボード本体やマニュアルにも載っているので、どのスロットを表しているのかが分かる。
M.2スロットには主にSSDを取り付ける。こちらもPCI Express接続が主流のため、拡張スロットと同じようにCPUとチップセットのどちらにつながっているかが記載されている。SSDの最大速度はPCI Expressのバージョンが大きく影響するため、使用するSSDの接続規格とM.2スロットが同じバージョンに対応していることを確認しておこう。
M.2スロットはPCI Express接続だけでなく、SATA接続のSSDにも対応する。ただし全てのスロットが両方に対応するわけではない。SATAのM.2 SSDを使用する場合は対応スロットの確認も重要だ。
最新プラットフォームではあまりないが、M.2スロットが他の端子やスロットと排他仕様になっていることもある。M.2のSSDが普及し始めた頃はプラットフォーム全体でPCI Expressのレーン数が足りず、M.2スロットにSSDを接続すると特定の拡張スロットが無効になることもあった。SATAに関しても同様で、M.2スロットにSATA SSDをつなぐと特定のSATA端子が無効になることもある。
MSIの「MEG Z590 UNIFY」の場合。M.2スロットの接続先をCPUに設定すると本来x16のPCI Expressスロットがx8での動作になること、特定のPCI ExpressスロットとM.2スロットが帯域を共有しており、同時利用には制約があることなどが注釈に書いてある。
USB端子
I/Oパネルと内部端子の区別に注意
USB端子の数はマザーボードを選ぶ際に気になる要素の一つだろう。通常、マザーボードのUSB端子の全てを使うことはできない。使用するPCケースによっても変わるため、よく確認しよう。マザーボードのスペック表では独特な表記があるため、きちんと読み取れるようになることは重要だ。
MSIの「PRO Z690-A」の例。速度と端子の数が記載されているが、I/Oパネルの端子と内部端子を合算しており、かっこ内に内訳を記載している。「back panel」とある場合はI/Oパネルの端子、「internal connector」は内部端子だ。
USB端子は、I/Oパネルに通常の端子が実装されていてそのまま使える場合と、ピンヘッダー等の内部端子で実装されている場合がある。内部端子はPCケースの前面端子とケーブルで接続して利用する。基本的に、内部端子のUSBはPCケースに接続できないと使えない(例外としてUSBの内部端子に接続する機器もある)。
多くの場合、PCケースの端子の数はマザーボードのピンヘッダーより少ない。さらに内部端子には種類が複数あるため、合わない場合は端子があっても使えないということもある。PCケースと合わせてよく確認しよう。
マザーボードのスペック表での記載はメーカーによってさまざま。USBだけ独立した項目を用意している場合や、内部端子とI/Oパネルの端子の一覧に含めてある場合など、メーカーによって大きく異なる。
端子と対応する内部ケーブルは以下の通り。
ファンとRGB LED用端子
同じように見えて使い分けが重要
ファン端子は一見同じように見え、実際に使い方も同じ。しかし、実はCPU用や水冷ポンプ用、ケースファン用など役割がそれぞれ異なる。そのため、同じファン端子でも別の名前が付いている。
MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFIの内部端子の一覧では、ファン端子はCPU用、水冷ポンプ用、ケースファン用で書き分けられている。「CPU fan connector」、「water-pump fan connector」、「system fan connectors」は全て4ピンのファン端子だ。
CPUファン
CPUファンはPC内でも特別重要なファンだ。故障で止まってしまうとCPUの冷却に深刻な影響を出してしまうため、ファンの回転数が一定以下になった場合にアラートを出す設定があるなど、他の端子より機能を多く備えていることが多い。
ポンプ用
ポンプ用端子は水冷クーラーを使用する際に使う。ファンと同様にポンプの回転数を検知できるほか、消費電力が大きいこともあるため、他のファン端子より大出力の電力に対応していることもある。
ケースファン
ケースファン用は「FAN1」「FAN2」のように番号が振られていることが多い。BIOS設定画面の表示に対応しており、どのファンをどの端子につないだか記録しておけばファンの場所ごとに回転数の設定ができる。
RGB LED用
RGB LED用端子には2種類ある。通常のRGBとアドレサブルRGBだ。通常のRGB端子はLEDの色を一括制御しかできない。全てのLEDを青にする、赤にするといった制御になる。アドレサブルRGBはLEDを個別に制御できるため、発光パターンの変更や専用ソフトで好きなパターンを作るといったことができる。上のスペック表では、アドレサブルRGB用は「RAINBOW LED connectors」と記載されている。マザーボード本体では、RGB端子は「RGB」と表記されることが多い。アドレサブルRGB端子はメーカーによって表記がまちまちなので、マニュアル等で確認しよう。
ネットワーク機能も注目
無線LAN搭載モデルも多い
ネットワーク機能は、自作PCでは有線LANを使っている人が多いだろう。長い間有線LAN端子は1Gbps(1000BASE-T)が主流だった。2022年現在、上位モデルではより高速な2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)に対応した端子を採用する例が増えている。ただし速度を生かすには他の機器も同等以上の有線LAN端子を備えている必要があるため、まだ活用できる環境は限定的だ。
無線LANを搭載したマザーボードも増えている。Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応している製品が多いが、2.4GHz帯と5GHz帯に加えて6GHz帯を使えるようにした規格のWi-Fi 6Eに対応していることもある。
無線LANの仕様はチャンネル幅と最大速度を確認しておこう。Wi-Fi 6/6Eで主に使われるチャンネル幅は80MHzと160MHz。80MHzで接続すると最大速度は半分の1.2Gbpsになるため、無線LANルーターも160MHzに対応していることを確認しておくと良い。
世代によって大きく変化するマザーボード
注意点も世代によってさまざま
マザーボードの仕様は、新しい機能やチップセットの仕様により、非常に複雑になる場合がある。記憶に新しいのは、PCI Express接続のSSDが普及し、マザーボードのPCI Expressのレーン数が足りなくなった時期に、複雑な排他仕様を採用したモデルが流行したことだろう。こうした新機能やトレンドによる複雑さは、最新規格にいち早く触れられる自作PCの宿命のようなものだ。
それでも、それぞれの項目のキーワードを覚えておけば、世代が変わっても情報を読み取りやすくなる。欲しい機能や仕様をスペック表から読み取れるようになれば、購入後に思っていたものと違ったというトラブルを避けられる。製品選びにも役立つはずだ。
(文・写真=SPOOL)
※ 本記事は執筆時の情報に基づいており、販売が既に終了している製品や、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
マザーボード製品のご紹介
株式会社アスクでは、最新のPCパーツや周辺機器など魅力的な製品を数多く取り扱っております。PCパーツの取り扱いメーカーや詳しい製品情報については下記ページをご覧ください。
PCパーツ製品 取り扱いメーカーのご紹介
マザーボードを探す